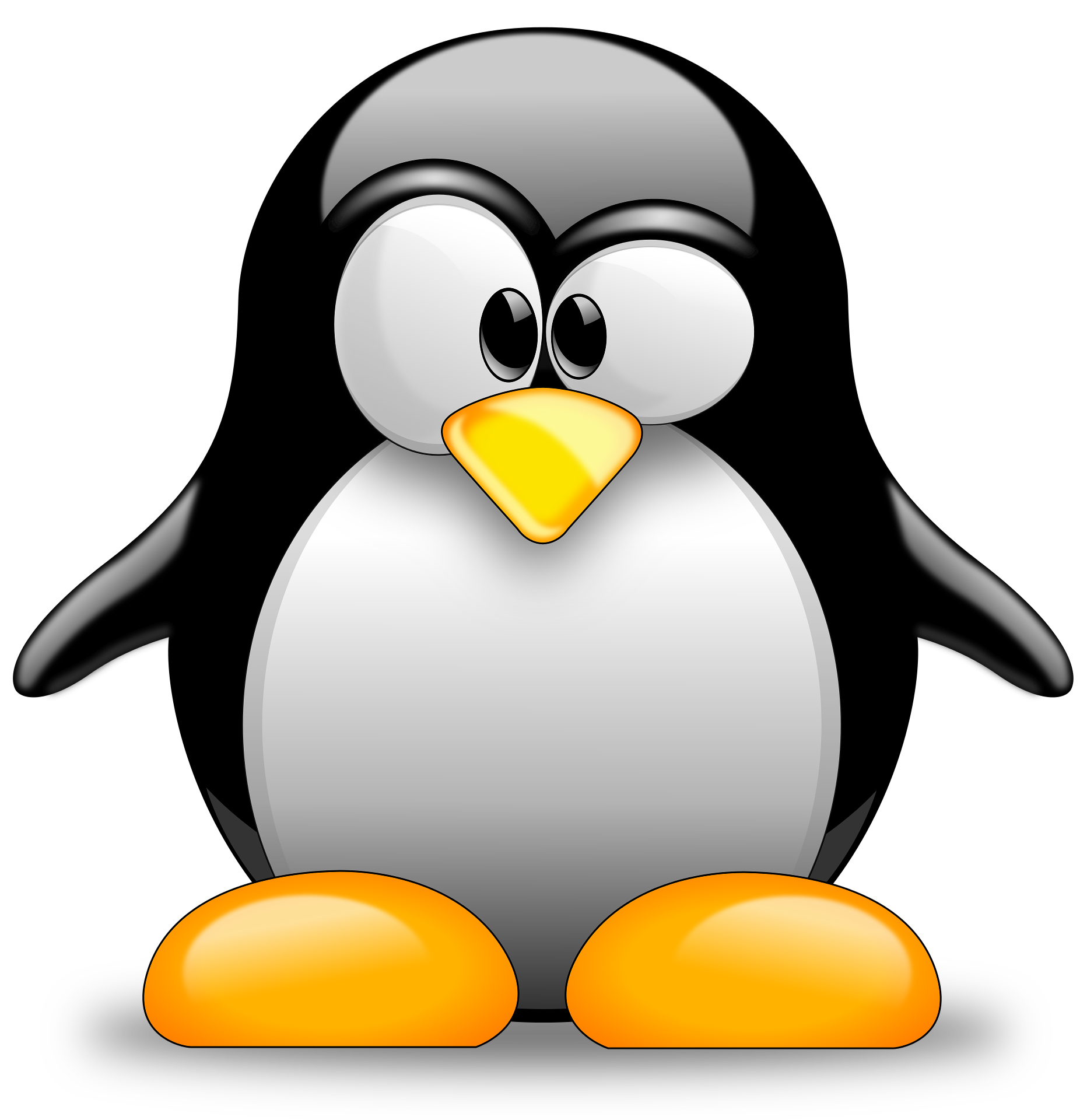みなさんこんにちは。
solaです。
普段使いのOSとしてLinuxは非常に現実的な選択肢になってきました。
そこで今回は普段使いでLinuxを活用するメリット、Linuxの強みについて話していきます
1.Linuxでゲームをプレイできるのか?
近年、Linuxでのゲーム環境は飛躍的に向上しています。Valve社のSteam Proton(Wineをベースにした互換レイヤー)が登場したことで、Windows用ゲームの大半がLinux上でそのまま動作するようになりました。例えば、Windows版でカクつきが問題となった「エルデンリング」が、Proton経由のLinuxではスムーズに動作するといった逆転現象も報告されています。多くのPCゲームが「購入すればLinuxでもそのまま遊べる」レベルに達しており、もはや「ゲーム目的でもLinuxで十分」と言える状況です。 パフォーマンス面でも、LinuxはWindowsと遜色ないフレームレートを発揮します。DirectXをVulkanに翻訳するProtonの処理コストはごくわずかで、高性能GPU環境でも平均10%前後のオーバーヘッドに留まります。実際、Proton利用時の性能ペナルティは「せいぜい10%程度で、90%の性能でも4Kゲームを楽しむには十分」と評価されています。さらにネイティブ対応のゲームであれば性能差はほぼ皆無で、一部ベンチマークではWindowsを上回る結果すら出ています。このように、最新タイトルでも描画品質を落とさず快適にプレイ可能です。 しかし、互換性の課題が完全にゼロになったわけではありません。
一部の高度なアンチチート機構(カーネルレベルのドライバ=ルートキット)を持つゲームはLinuxで動作しない場合があります。
例えば「League of Legends」は、運営がアンチチートにルートキットを導入した結果、Linux上で起動できなくなりました。
このようなケースは稀ですが、Windows専用のサービスに依存するゲームは注意が必要です。
また、Steam以外で入手したゲームや古いタイトルでは、Wineやエミュレータの細かな設定調整が必要になることもあります。
ただ、昔に比べればLinux上でゲームをプレイする体験は大幅に改善され、多くのタイトルが難しい設定なしで動作する段階に来ています。
2. クリエイティブ用途での利点と課題
Linuxには様々なクリエイティブソフトが揃っています。
画像編集ならGIMPやKrita、ベクター描画はInkscape、3DCG制作はBlender、動画編集はDaVinci ResolveやKdenlive、Shotcut、音楽制作にはLMMSやArdourといった具合に、用途ごとに様々なオープンソースのプロ向けソフトウェアが無料で利用可能です。
しかもこれらはクロスプラットフォーム対応が多く、Linuxでも安定して動作します。さらに、DaVinci Resolve(カラーグレーディング・動画編集ソフト)やAutodesk Mayaは業界でも人気な非常に多機能なソフトです。
実際、DaVinci Resolveは元々Linux専用機器向けに開発されていた経緯もあり、現在もCentOS/RedHat系のディストリビューションを中心に公式サポートされています。
このように、クリエイティブ制作自体はLinux上でも十分に可能です。 しかしソフトウェアの選択肢という点では注意が必要です。業界標準のAdobe製品(PhotoshopやIllustrator、Premiere Pro、After Effectsなど)はLinux非対応であり、現状Linux環境では公式に利用できません。代替としてGIMPやInkscapeで多くの機能は賄えるものの、機能面や互換性でAdobe製品に及ばないケースもあります。
また、他のメンバーとの共同作業でAdobeファイル形式をやり取りする場合、Linuxユーザーだけ別ソフトを使うことによるワークフローの違いが生じる懸念もあります。
音楽制作でも、ProToolsやFL Studioなど一般的な商用DAWはLinux対応していないため、代替ソフトの習熟が必要です(ただしReaperやBitwigのようにLinux版を提供する例もあります)。
必要なクリエイティブソフトがLinuxで利用可能かを事前に確認し、場合によっては代替ソフトへの乗り換えやWineによる動作(成功すればPhotoshop等もWineで動く報告があります)を検討する必要があります。
パフォーマンス面では、Linuxと他OSで大きな差はないか、場合によってはLinuxが有利です。クロスプラットフォームなBlenderなどは同一ハードウェアで動作がほぼ同等ですし、前述のDaVinci ResolveにおいてもLinux版とWindows版で処理速度は概ね拮抗しています。
Puget Systemsの検証では「多くの作業負荷においてCentOSとWindows 10の性能差はごくわずかで、OSによって作業効率が大きく左右されることはない」と結論付けています。一部エフェクト適用時にWindowsが平均数FPSだけ上回るケースがありましたが、その程度の差ではOS選択の決め手にはならないとも指摘されています。ただし、Linux版ソフト固有の制限にも留意すべきです。例えばDaVinci ResolveのLinux版は対応オーディオデバイスが限定される等の制約があり(Blackmagic社の専用機器を前提としている部分)、用途によってはWindows/Mac版より不便な点もあります。このように細かな課題こそあるものの、クリエイティブ作業自体はLinuxでも高い生産性で行うことが可能です。普段からオープンソースツールに慣れておけば、Windows/Macに遜色ないクオリティの作品制作を十分に実現できるでしょう。
Linux上で3DCG制作ソフトであるBlenderを動かすとネイティブに動作し、他OS以上の性能を発揮する
3. 事務作業
文書作成や表計算などの事務作業でも、Linuxは一通りの環境が無料で手に入ります。代表的なオフィススイートであるLibreOfficeは、Word/Excel/PowerPointに相当する機能を備えており、オフラインでも快適に利用できます。
基本的な文書や表ならLibreOfficeで問題なく作成・編集できますし、Googleドキュメント/スプレッドシート等のオンラインツールもブラウザ経由でWindows同様に利用可能です。
日常的な文書作成、メールやチャット、スケジュール管理といった業務はLinuxでほぼ網羅できます。例えばPDF閲覧も標準のドキュメントビューワで可能であり、簡単な注釈付け程度であればOkularなどで対応できます。 注意点はMicrosoft Officeとの互換性です。LibreOfficeでもWordやExcelのファイルを開けますが、複雑な書式やレイアウトは崩れる場合があります。実際、LibreOfficeで作成したファイルをMicrosoft Officeで開くとレイアウトが乱れたり、逆にWordの.docxファイルをLibreOfficeで開くとページ割りが変化することがあります。また、Excelのマクロや高度なVBA、特殊な関数はLibreOffice Calcでは正常動作しないことがあります。このため、社内外でOffice文書を頻繁にやりとりする場合、完全な互換性確保が課題となります。ただしLibreOffice側も互換性向上のアップデートを継続しており、常に最新版を使う・保存時にMicrosoft Office形式(docx/xlsx/pptx)を選ぶ、といった対策で問題を極力減らすことができます。事前に相手先での表示崩れを確認し、必要に応じて調整する運用で多くのケースは乗り越えられます。 そのほかの事務系ソフトについても、近年はWebアプリやクロスプラットフォームソフトの普及でLinuxでも困るシーンが減りました。例えばメールクライアントはThunderbirdやEvolutionがありますし、ビデオ会議もZoomやMicrosoft TeamsのLinux版クライアントが提供されています。クラウドストレージもDropboxやGoogle DriveはWeb経由で利用可能です(Google Driveは有志クライアントも存在)。PDF編集については、LibreOffice Drawで簡易的な編集ができるほか、より高度な編集にはLinux対応の「Master PDF Editor」などのツールも利用できます(Adobe AcrobatのLinux版は無いため代替ソフトを使用)。総じて、一般的なオフィス業務はLinuxでほぼ支障なくこなせると言えます。ただし、社内システムがWindowsアプリ前提だったり、特殊な会計ソフト・CADソフトなど特定業務ソフトがLinux非対応の場合は引き続きWindowsが必要です。このようなケースではブラウザ版サービスへの移行や、どうしても必要ならWine/仮想マシンでのWindows利用といった対策を検討することになります。
4. パフォーマンス・安定性・セキュリティ パフォーマンス(軽量性)
一般にLinuxは動作が軽快で、古いPCでもサクサク動く傾向があります。これはWindowsやmacOSに比べてGUIがシンプルで、不要な常駐サービスが少ないことによります。
例えば、サポート切れの旧型PCにLinuxを入れ直したところ動作が大幅に改善する、といった事例も珍しくありません。
実際、多くのディストリビューションでメモリ消費やディスク占有が控えめに設計されており、最新ハードはもちろんローエンド機でも軽快に使えます。
用途に合わせて軽量なデスクトップ環境(XfceやLXQt等)を選べば、低スペックマシン上でも快適に作業できるでしょう。
個人的にはHyprlandというデスクトップ環境がおすすめです。
サイバーなデザインで唯一無二のかっこよさがあります。
動作も比較的軽いです。
他にも、Linuxは高い安定性で知られ、長期間連続稼働しても動作が安定しています。
サーバー用途でLinuxが支持されている主な理由の一つがその安定性であり、企業向けディストリでは稼働時間数百日以上というケースもあります。
デスクトップ用途でも、カーネルパニック(クラッシュ)はまれで、適切なドライバを使用していればOS自体がフリーズしたり再起動を強要される場面は少ないです。Windowsのような突然のブルースクリーンや強制アップデート後の再起動に悩まされにくい点は大きな利点です。
また、複数のディストリビューションから自分の用途に合ったものを選べるため、安定重視ならLTS版(長期サポート版)を選択するといった運用も可能です。もっとも、Rolling版(常に最新ソフトに更新されるタイプ)ではアップデートに起因する不具合が稀に発生するため、安定性を重視する場合は実績のある安定版を選ぶのがおすすめです。
セキュリティ: ウイルスやマルウェアの脅威が低い点もLinuxを日常利用するメリットです。Linux向けのウイルスが皆無なわけではありませんが、その数は非常に少なく、実際に感染に遭遇する可能性は極めて低いのが現状です。理由として、(1) Linuxはユーザー権限が厳格に分離されており、仮にウイルスが実行されてもユーザー自身の権限内でしか動けずシステム全体に広がりにくいこと、(2) Windowsのようにウイルス拡散に悪用されやすいマクロ機能(OfficeマクロやActiveX等)がLinux環境にはほとんど無いこと、(3) ほぼ全てのソフトがオープンソースでソースコードが公開されているためウイルスを仕込むのが困難なこと、などが挙げられています。
加えてLinuxデスクトップ利用者数自体が少ないため標的として割に合わない、という点も大きいでしょう。
こうした理由から「LinuxではWindowsほどウイルス対策ソフトに神経質にならなくてもよい」と言われます。
ただし過信は禁物で、ゼロではないリスクに備えてOSアップデートを怠らないことが重要です。
幸いLinuxはパッケージ管理システムによる一元アップデートが可能で、OSとアプリのセキュリティ修正をコマンド一つで速やかに適用できます。
脆弱性が発覚した際も、ディストリビューションのリポジトリ経由でパッチが即座に配布されるため対応が早く、ユーザーは容易にシステムを最新の安全な状態に保てます。結果としてウイルスに感染しにくいだけでなく、仮に問題が見つかっても迅速にアップデートで対処できる安心感があります。ファイヤーウォール機能やアクセス権管理も標準で強力なものが備わっており、総合的に見てLinuxは日常利用においてセキュリティ面で優位性が高いプラットフォームと言えます。
5. LinuxをメインOSにする際のデメリットと対策
上述のように多くのメリットがある一方、Linuxを日常の主OSとするにあたっていくつか乗り越えるべき課題も存在します。
ここでは代表的なデメリットと、その対策・回避策について整理します。 ドライバ・ハードウェアの互換性: Windowsに比べると、Linux対応のデバイスドライバが提供されていないハードウェアがあります。
近年はプリンターやスキャナーも含め対応状況は改善していますが、それでも特殊な周辺機器(ごく一部のUSBデバイス、最新のゲーム用デバイスなど)では公式ドライバが無い場合があります。例えば、メーカー純正のWindowsソフトで動かすことを前提とした機器の場合、Linuxではすぐ使えないことがあります。
また、新発売のGPUや最新ノートPCでは、発売直後にLinuxカーネル側の対応が追いつかず一時的にうまく動かないこともあります。対策: 購入前にLinux対応状況を調べることが第一です。
LinuxコミュニティやハードウェアDBで動作報告を確認し、互換性の高い機器を選ぶと安心です。既に手持ちの機器でドライバ非対応の場合、有志が開発したドライバや代替手段が提供されていないか検索してみましょう。
カーネルに組み込まれていない新デバイスの場合、ソースコードからドライバをコンパイルして導入する手順がネット上で共有されていることもあります。例えば特定のWi-FiアダプタをUbuntuで使うためにカーネルモジュールを自前でビルドした、という例もあります。難しいように聞こえますが、多くの場合は手順通りにコマンドを実行すれば適用でき、以降は通常通り利用可能となります。
それでも対応が難しい場合は、どうしても必要な機器だけWindowsマシンに接続して使う、という割り切りも一案です。
ソフトウェアが動作しない可能性: 特定のWindows専用アプリ(業務ソフトや娯楽ソフト含む)がLinux上では使えないケースがあります。前述したAdobe製品や一部のゲームなどが典型例です。
対策としましては、 代替ソフトの検討が最優先策です。Linuxには数え切れないほど豊富な代替フリーソフトがあるため、まずは同等の機能を持つアプリを探してみましょう。それでも代替が難しい場合は、Wineを使ってそのWindowsアプリが動くか試す価値があります。Wine開発は活発で、多くのWindowsアプリが意外と普通に動作します(MS Office 2010年代の版や、Adobe CS旧版のインストール報告などがあります)。また、仮想マシン(VM)上にWindowsを動かし、その中で当該アプリを使う方法もあります。最近のPCスペックならホストLinux上でVirtualBoxやVMwareを動かしても十分実用的な速度が出ます。どうしてもリアルタイム性が必要な用途(3Dゲーム等)でなければVM内Windowsでも支障ないでしょう。
最終手段としてデュアルブートでWindowsを残しておき、必要時に切り替える方法もあります。ただしデュアルブートは手間が増えるため、可能な限りLinux上で完結できる代替手段を模索することをおすすめします。
Linux初心者が陥りやすいトラブル: Windowsに慣れたユーザーが最初にLinuxを使う際、操作や概念の違いに戸惑うことがあります。例えばソフトのインストール一つ取っても、Linuxでは基本的にディストリのパッケージ管理(ソフトウェアセンターやコマンド)経由で行うため、初めてだと勝手が違います。また不慣れなうちは、問題発生時にターミナルでの調査・対処が求められる場面もあります。対策: まずはユーザーフレンドリーなディストリビューションを選ぶのが肝要です。
UbuntuやLinux Mint、Pop!_OSなどは初学者向けにドキュメントやコミュニティも充実しており、日本語環境も整っています。
次に、分からないことがあればインターネットで積極的に調べましょう。Linuxはユーザー層が技術志向なこともあり、トラブル解決方法がフォーラムやブログに詳しく蓄積されています。
「○○ Linux できない」で検索すれば大抵の答えは見つかります。
重要なのは、最初から完璧を目指しすぎないことです。必要に応じてWindowsとの併用期間を設けつつ、日常的な作業を少しずつLinuxに置き換えていけば、無理なく移行できるでしょう。幸いDaVinci ResolveやChromeなど多くの人にとって馴染みのアプリも多く、思ったよりすぐ慣れるとの声もあります。万一システムを誤操作で壊しても、Linuxはオープンソースゆえにコミュニティの助けを借りて復旧できますし、最悪再インストールしても基本無料である分ダメージは小さいです。Linuxに慣れるまでの学習コストは確かに存在しますが、その先には自由で快適なコンピューティング環境が待っていると言えるでしょう。
カフェなどでかっこよくカスタムしたデスクトップ環境をチラ見せしながらドヤりましょう。
まとめ
Linuxを普段使いのメインOSとすること得られるメリットは多岐にわたります。無料で入手できるOSとソフト群によるコスト削減、軽快な動作と高い安定性、ウイルスに強いセキュリティ、そして近年飛躍的に改善したゲーム対応や豊富なクリエイティブソフトの存在、見た目のかっこよさは非常に大きな魅力です。
一方で、特定ソフトの非対応やドライバ問題、慣れないうちは操作に戸惑うといったデメリットもあります。しかしこれらの多くは代替手段の活用や事前リサーチ、コミュニティからの情報収集によって十分対処可能です。総合的に見れば、Linuxは日常利用において現実的な選択肢となってきており、自分の用途と照らし合わせてメリットがデメリットを上回るなら、メインOSとして検討する価値はとても大きいです。
自分好みに環境をカスタマイズしながら、安全・快適に美しくパソコンを使いこなせるのは、Linuxならではの魅力です。